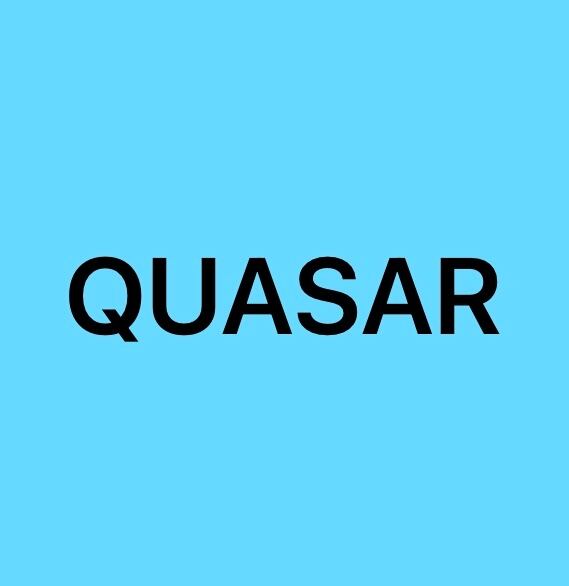2024/12/22 08:31
弊サービスでは各種ハラスメントに関する規定を明確に定めております。
その中から、「パワーハラスメント」の項目について引用してみます。
◆
弊サービスではインストラクターとお客様の間で序列を付けるようなことはせず、あくまでも両者は「対等」であると考えています。
したがって、旧来の教習所では当たり前のようにあった「怒鳴る」「モノに当たる」「暴力行為をする」「詰問する」等といったことをしてお客様を萎縮させるような行為を弊サービスでは明確に禁じております。
大概のケースでは冷静に、根気強く指導することにより改善するものばかりです。
弊サービスのお客様は他業種で第一線のご活躍をされている方も多く、お客様から学ぶことも多々ありますので、それに感謝しつつ日々業務にあたっております。
※ただし、以下の場合は例外として強めの注意喚起をすることがありますが、いずれも「事故防止・交通の円滑化を図る」事が目的のため、お客様を攻撃する意図はありません。
・お客様の運転が原因で他車(者)に直接的な危害を加える恐れがある場合
・お客様の判断不良により、他車(者)の通行妨害となるような運転行動が見られた場合
◆
つまりは、旧来の教習所では当たり前であった、感情に任せて「怒る」指導は当然のことながら弊サービスからは「原則として」排除しているということです。
「怒る」ことにはメリットがあまりないからです。
ただし、そうは言っても簡単に人を傷つけることが出来る車を操作するわけですから、全てのケースで全く注意を与えないかというと、そういうわけではありません。
先述のパワーハラスメント規定の最後にもありますように、繰り返しにはなりますが、
・お客様の運転が原因で他車(者)に直接的な危害を加える恐れがある場合
・お客様の判断不良により、他車(者)の通行妨害となるような運転行動が見られた場合
は多少強めの注意喚起をすることがあります。
先日のブログでも取り上げましたように、道路上の危険を防止し、円滑性を保たないといけないわけなので、ここから逸脱することがあれば、それはお客様に「何が危険なのか」「ではどうすれば良かったのか」をお伝えしなくてはなりません。
ただ、お客様がミスを起こす瞬間にはゆっくり解説している余裕はありませんので、その瞬間だけは他の危険が発生しないように簡単な注意・指示を与えます。場合により強い言い方になるかもしれません。
その後の解説において丁寧にイラストや教本を用いて改善策を伝えるようにしています。
ではどういうケースで注意を与えることが多いのか、代表例をお伝えします。
・こちらが指示した動きと異なる動きを取った場合
(例、進行方向選択ミスなど)
・行ける状況なのに、お客様の判断不良により急停止、あるいは進行しない場合
(例、信号が変わる状況で交差点内で停止し続けるなど)
・確認不足による見落とし
などがあります。
「怒る」ことはあってはなりませんが、危険防止のため、円滑維持のための「指導」は当然あるべきです。
その指導には「感情」は必要ありません。必要なのは「理論的な説明」だけです。