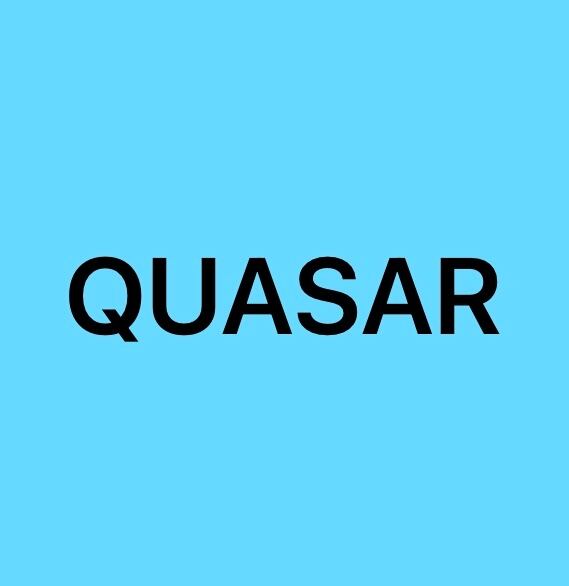2024/12/22 08:29
道路を利用する人全てには「道路交通法を守らなければならない」という「建前」があります。
全員が道路交通法を遵守していれば、事故が起こらない円滑な道路環境が醸成されるはずです。
ところが、現実はそうではありません。
道路交通法を少し逸脱して道路を利用されているのが現状です。これが「本音」でしょう。
ここでまず、建前である道路交通法の目的(第一条)を再確認しましょう。
「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」
とあります。
つまりは「道路交通法を守れば道路上の危険も防げるし円滑に流れますよね」となっているはずなのですが…
現実はそうでもないようです。
道路交通法を守ることにより、現実的にはかえって円滑性が損なわれている面が出てきてしまうのです。
代表的なものとしてはスピードコントロール関係が挙げられるでしょう。
(規制速度、徐行や一時停止の義務がある場合や場所など)
これが既に法律(建前)と現状(本音)が乖離してしまっているケースが大多数です。乖離しているが故に、建前を守ろうとすると最悪、大多数の流れから見ると厄介な存在となってしまうのです。
本末転倒ですよね。
最初は建前を守っていたはずなのに、いつしか周りに合わせて「少しくらいはいいよね」と規制速度を上回って走ったり、一時停止場所を徐行で通過したりするのです。
ではなぜ道路交通法を少し逸脱するという「拡大解釈」が発生し得るのでしょうか?
あくまでも仮説ですが、
・40キロ規制の道路を50キロ(あるいはそれ以上)で走ってもあまり不都合がないことにみんなが気づいてしまったため。仮に飛び出しがあっても何とか回避できてしまったという「負の経験値」が身についてしまったため。
・一時停止を徐行で進んでも著しい危険がないし、優先道路から何かが来たとしてもすぐに何とか止まれるということにみんなが気づいてしまったため。
速度関係以外で例えるなら、
・ウィンカーを多少出し遅れてもそんなに致命的な危険が生じなかったから
・多少右左折の寄せが甘かったとしてもみんな回避してくれている
などといった色々な「悪い意味での経験値」が積み重なった結果が、「道路交通法を多少逸脱しても何とかなるよね」と曲解されるようになり、いつしかそれが大多数となってしまったことが最大の要因なのではないかと思います。
それは言うまでもなく、良くないことです。
しかし、ここで今更道路利用者全員に道路交通法を遵守するように呼びかけたところで「いやいや今までこのやり方で何ともなかったよ」と大多数の人から反論されてしまうのが関の山なのでそれこそ現実的ではありません。
それでも残念ながら現実問題、事故やトラブルは起きています。
これは「道路交通法を"大きく"逸脱したから」「運転操作そのものを誤ったから」「そもそも見ていなかったから」…最近では「自分さえ良ければいいと考える人が増えたから」といった要素が強いのではないかと思います。
決してこの記事は「道路交通法を破る」ことを推進しているわけではありません。当然ベースとして守られるべきではあります。
しかし、現実的にはそうではないケースもあるため、それは何でなの?ということをちょっとだけ突き詰めることを目的とした内容です。
ということは、指導する上でも「みんなが道路交通法を多少破っている前提→だからこういう動きをしてくださいね」といった柱で物事を伝えていかないと、現実に即していない運転となってしまうのです。当然ですが、道路交通法のキモは押さえた指導はしますのでご安心くださいね。